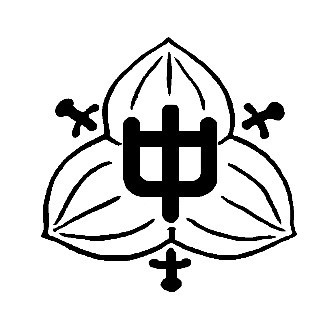季節は晩秋 (11月10日)
- 公開日
- 2013/11/10
- 更新日
- 2013/11/10
隅田中日記
「天声人語」11月10日 より
サクランボは色っぽい流行歌になったし、リンゴは青春詩歌に無くてはならない。そこへいくと柿は、同じフルーツながら「わび、さび」のたたずまいが渋い。このあいだ東京西郊の武蔵野を歩いたら、熟した実が斜陽に赤く照っていた▼筆者が育った田舎にも、あちこちに柿の木があった。竿(さお)でもいでよく食べたものだ。今はそうでもないらしい。何年か前の川柳欄に〈熟れ柿の少しも減らず少子国〉と載っていた。これでは「木守(きまも)り柿」の風習も意味をなさない▼取り尽くさず、いくつか木に残す実をそう呼んだ。来年もよく実るように、お守りとして、あるいは鳥のために残しておくと聞かされた。葉の散った枝にぶら下がる光景を、懐かしく思い出す方もおいでだろう▼〈ふるさとを捨つる勿(なか)れと柿赤し〉山崎みのる。この国の秋景色にしみじみ似合う柿を、京都生まれの名料理人だった辻嘉一(かいち)さんが「国果」と言っていた。なるほどと思ったものだが、近頃は年若い世代の人気がいま一つなのだという▼皮をむきにくいためらしい。昨今はミカンの皮むきも面倒がられると聞く。日本人の手はいつしか怠け癖がついたようだ。丸ごと口に入れて腹に収まるイチゴや種なしブドウが今は人気者である▼暦は立冬を過ぎて、季節は晩秋。いつぞや小欄で冬枯れに向かう11月のイメージを「いささか不遇」と書いたら、霜月擁護のお便りをずいぶん頂いた。冷雨のあとには小春日和がめぐって、そして、ふるさとの柿はいよいよ赤い